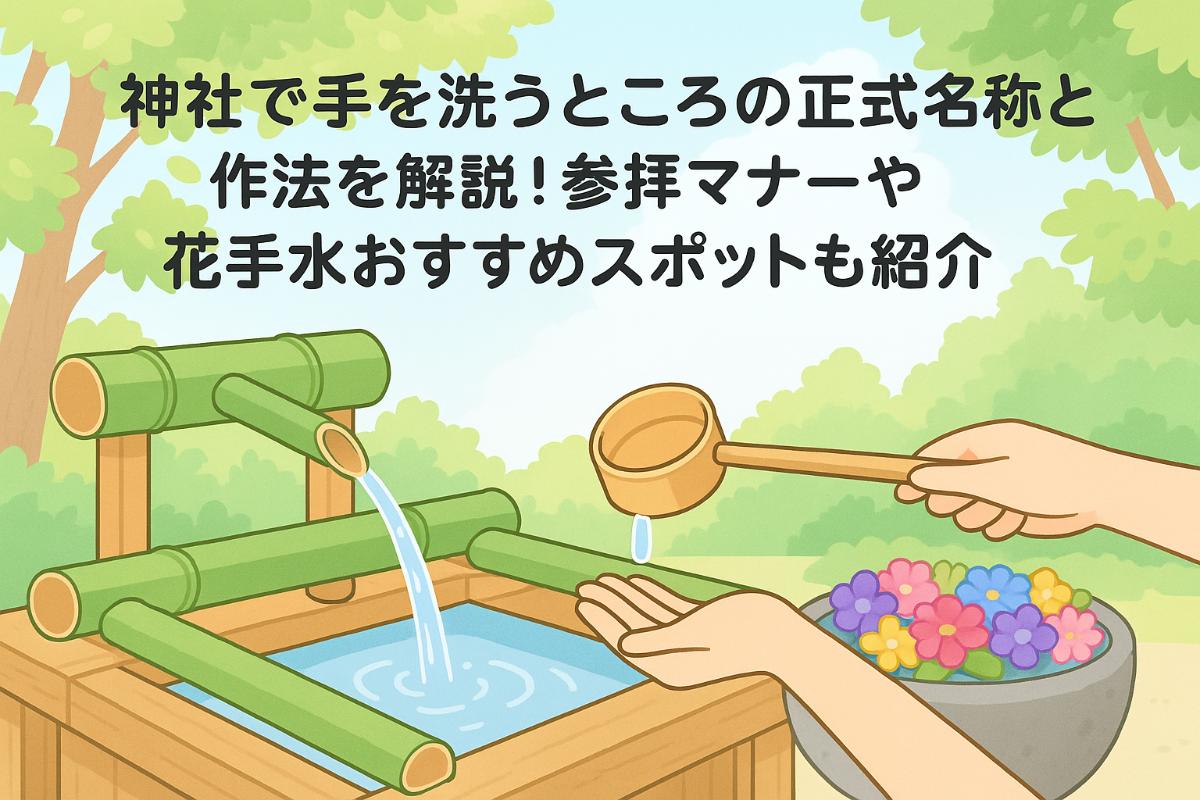神社で手を洗うところの正式名称と作法を解説!参拝マナーや花手水おすすめスポットも紹介
神社の手を洗う場所=手水舎(ちょうずや)」、その正式名称や意味をご存知ですか?日本全国には【約8万社】の神社があり、そのほとんどに手水舎が設けられています。しかし、「どの順番で手を洗えばいいの?」「柄杓(ひしゃく)はどう持つの?」と、正しい作法やマナーがよくわからず戸惑った経験はありませんか。
手水舎の歴史は古く、奈良時代には既に神聖な儀式として定着しており、現代でも京都や東京などの有名神社で多様なデザインや「花手水」など新たな文化が生まれています。正しい手水の作法を知ることで、参拝がより深く心に残る体験へと変わります。
この記事では、【手水舎の名称や由来】【歴史的背景や地域差】【最新の衛生対策】まで、具体的な手順とともにわかりやすく解説。「これでもう迷わない!」と思える、実践的な知識と現場で役立つポイントを余すことなくご紹介します。
大稲荷神社は、古くから地域に親しまれている神社で、心安らぐひとときを提供しています。歴史的な背景を持ち、神聖な空間の中で心を込めたお祓いや祈願を行っております。境内では、静寂な雰囲気の中で自然と調和したひとときを楽しんでいただけます。地元の方々はもちろん、訪れる方々にとっても安らぎと力を与える場所となっております。どうぞ一度お参りいただき、神聖な空間を体験してください。

| 大稲荷神社 | |
|---|---|
| 住所 | 〒250-0045神奈川県小田原市城山1-22-1 |
| 電話 | 090-3478-4699 |
神社で手を洗うところの正式名称と歴史的背景
手水舎の読み方と名称の違い
神社で手や口を清める場所は「手水舎」と呼ばれますが、他にも「手水場」「手水所」といった名称が使われています。読み方や意味の違いを整理します。
| 名称 | 読み方 | 意味・用途 |
| 手水舎 | ちょうずや | 最も一般的。屋根付きの建築物。 |
| 手水場 | ちょうずば | 屋根がない場合も含む。 |
| 手水所 | ちょうずしょ | 施設名として案内板などに使われる |
| 手水屋 | ちょうずや | 古い表記。手水舎と同意。 |
手水舎の起源と歴史的意義
手水舎の起源は古代日本の禊(みそぎ)や清めの文化に遡ります。神社の境内に入る前に手や口を清めることで、神様に敬意を表し、心身を清浄に保つ意味があります。
元々は川や湧き水で禊をしていましたが、時代とともに建築物としての手水舎が登場しました。現在も多くの神社で、龍の口から水が流れる「龍の手水舎」など、個性的な意匠が見られます。伊勢神宮や明治神宮といった全国の有名神社でも、立派な手水舎が参拝者を迎えています。
手水文化の地域差と発展
手水舎は地域や神社ごとに形や装飾が異なります。京都や東京など都市部では伝統的な建築が多く、地方では自然石を使った素朴な手水所も存在します。近年では「花手水」と呼ばれる新しい文化が登場し、季節ごとに色とりどりの花が手水鉢を彩ります。
この「花手水」は写真スポットとしても人気で、全国各地の神社でイベントとして取り入れられています。また、コロナ禍以降は柄杓を使わず流水で清めるスタイルや、消毒液を併用するなど、時代に合わせた配慮も見られます。
手水舎の正しい使い方と作法の詳細ガイド
基本的な手水の手順とマナー
神社で手を洗うところは「手水舎(ちょうずや、てみずしゃ)」と呼ばれ、参拝の前に心身を清める大切な場所です。以下の手順と順番を守ることで、正しい作法が身につきます。
- 手水舎の前で軽く一礼します。
- 柄杓(ひしゃく)を右手で持ち、水を汲んで左手を洗います。
- 柄杓を左手に持ち替え、右手を洗います。
- 再び右手に持ち替え、左手に水を受けて口をすすぎます。口をすすいだ水は足元へ静かに吐き出します。
- もう一度左手を洗います。
- 最後に柄杓を立てて残った水で柄の部分を洗い、元の位置に戻します。
ポイント
- 口をすすぐ際は直接柄杓を口につけず、左手に水を受けてから行います。
- 順番を守り、静かに行動することが大切です。
柄杓の持ち方と水の量の目安
柄杓は一度だけ水を汲み、必要な作法をその一杯で済ませるのが基本です。水の量は多すぎず、周囲に飛び散らせないよう注意しましょう。
| 項目 | 詳細説明 |
| 柄杓の持ち方 | 最初は右手で持ち、途中で左手に持ち替える |
| 水の汲み方 | 一度だけ汲み、全手順を一杯で行う |
| 柄杓の戻し方 | 最後に柄の部分も水で洗い、元の位置へ丁寧に戻す |
| 使い終わった後 | 周囲に水が飛ばないよう静かに動作する |
正しい持ち方と使い方を守ることで、神聖な場所への敬意を示せます。
手水舎利用時の心構えと注意点
手水舎は神様の前で自らを清める神聖な場所です。静かに心を落ち着けて利用しましょう。以下の点にも注意してください。
- 他の参拝者と譲り合い、混雑時は順番を守ります。
- 柄杓や水を粗末に扱わないようにします。
- 写真撮影は周囲の迷惑にならないよう配慮します。
敬意と礼儀を大切にし、神社本来の文化や伝統を尊重しましょう。
感染症対策下での手水舎利用法
近年は感染症対策のため、手水舎の利用に制限がある場合があります。下記のような代替方法も広まりつつあります。
- 柄杓が撤去されている場合は、流水で手だけを洗う。
- 口をすすぐ動作は省略し、手のみを清める。
- アルコール消毒液が設置されている場合は、そちらも活用する。
各神社の案内や公式情報を事前に確認し、案内に従って行動するのが安心です。
花手水(はなちょうず)の魅力と全国の注目スポット
花手水の起源と意味
花手水は、神社や寺院の手を洗うところ「手水舎」で季節の花を浮かべて彩る美しい文化です。日本の伝統的な手水舎は、参拝前に心身を清めるための場所で、その歴史は古く、建築や装飾にも地域独自の工夫が見られます。もともと手水舎(読み方:てみずしゃ、ちょうずや)は清めの儀式として重要視されてきましたが、近年では花を浮かべることで訪れる人々に癒やしや安らぎを与えるスポットとしても人気が高まっています。特に、インスタグラムなどSNSでの写真映えが話題となり、全国各地で花手水を楽しめる神社や寺院が増えています。
季節ごとの花手水の特徴と作り方
春には桜や菜の花、夏は紫陽花や蓮、秋にはコスモスや菊、冬は椿や南天など、その時期ごとの美しい花が手水舎を彩ります。花手水の作り方は、まず手水鉢や桶に新鮮な水を張り、季節の花を浮かべるだけ。定期的に水を替え、花が傷んだら新しいものと交換するのがポイントです。飾る花は地域やその年ごとのイベントに合わせて選ばれることも多く、訪れるたびに違った表情を楽しめます。花の種類と色のバランスを意識することで、より華やかで整った印象になります。
- 春:桜、菜の花
- 夏:紫陽花、蓮
- 秋:コスモス、菊
- 冬:椿、南天
全国の人気花手水スポット一覧
全国には、花手水が有名な神社や寺院が点在しています。特に東京、三重、京都は、花手水スポットとして多くの人が訪れる地域です。以下に主要なスポットを紹介します。
| 地域 | 神社・寺院名 | 特徴 |
| 東京 | 日枝神社 | 都心でアクセスが良く、四季折々の花手水が楽しめる |
| 京都 | 楊谷寺(柳谷観音) | 「花手水発祥の地」とも言われ、花手水の種類が豊富 |
| 三重 | 伊勢神宮 | 歴史を感じる手水舎と、伝統的な花手水が魅力 |
| 埼玉 | 行田八幡神社 | 色鮮やかな花手水と、季節ごとのイベントが充実 |
| 神奈川 | 江島神社 | 海の近くで独特の花手水が楽しめる |
手水舎から参拝までの正しい流れとマナー
手水舎は神社の入り口近くに設置されており、参拝前に心身を清めるための大切な場所です。手水舎の正式名称は「てみずや」や「ちょうずしゃ」と読み、神社によって「手水所」「手水場」「手水屋」など呼び方が異なります。最近では美しい花で彩られた「花手水」が人気を集めており、京都や東京の有名神社でも話題です。手水舎には龍の彫刻が施されていることも多く、神聖な雰囲気を演出しています。
正しい手水のやり方は以下の通りです。
- 柄杓を右手で持ち、左手を清める
- 柄杓を左手に持ち替え、右手を清める
- 再び右手に持ち替え、左手に水を受けて口をすすぐ(※直接柄杓に口をつけない)
- 口をすすいだ水は足元に静かに吐き出す
- もう一度左手を洗い、最後に柄杓の柄を立てて残りの水で柄を清める
手水舎利用後の参拝手順
手水舎で心身を清めた後は、参道の中央を避けて本殿へ向かいます。中央は神様の通り道とされているため、控えめな位置を歩くのがマナーです。静かに歩みを進め、境内では大声やスマートフォンの使用は控えましょう。
本殿前では、まず軽く一礼し、お賽銭を入れます。鈴がある場合は静かに鳴らし、二礼二拍手一礼の作法で参拝します。お願いごとは心静かに伝え、最後にもう一度一礼して退きます。
| 参拝の流れ | ポイント |
| 1. 手水舎で清める | 正しい順番で丁寧に |
| 2. 参道を歩く | 中央を避ける |
| 3. 本殿で一礼 | 静かに |
| 4. お賽銭 | 音を立てずに優しく |
| 5. 鈴を鳴らす | ゆっくりと |
| 6. 二礼二拍手一礼 | 基本作法を守る |
服装や参拝時のマナー
神社参拝にふさわしい服装は、清潔感があり派手すぎないものがおすすめです。Tシャツやジーンズでも問題ありませんが、極端な露出やサンダルは避けるとよいでしょう。帽子は参拝時には脱ぐのが礼儀です。雨天時も傘を閉じてから本殿に進むよう心がけます。
礼儀としては、歩く際に大声で話さず、写真撮影も控えめに。神聖な空気を大切にし、他の参拝者への配慮も忘れないことが重要です。手水舎や本殿前では順番を守り、混雑時は譲り合いの気持ちを持ちましょう。
参拝中のよくあるトラブルと対処法
手水舎を忘れてしまった場合や、手水舎が設置されていない神社もあります。その際は、心の中で「清めの儀式を省略します」と静かに唱えてから参拝しても問題ありません。手を洗う場所が花手水の場合も、基本の作法は同じです。柄杓がない場合は、直接水を手ですくって清めても大丈夫です。
感染症対策で手水舎が使用できない場合は、持参したウェットティッシュや除菌シートで手を拭くと良いでしょう。口をすすぐ作法も、コロナ禍では省略が推奨されています。いずれの場合も、神様や他の参拝者への敬意を第一に考えることが大切です。
よくあるトラブルと対応策を下記のテーブルでまとめます。
| トラブル内容 | 推奨される対応方法 |
| 手水舎がない | 心の中で清めを意識する |
| 柄杓がない | 手で水をすくう |
| 口をすすげない | 省略しても良い |
| 手水舎が花手水 | 基本の作法を守る |
| 服装が不適切かも | 清潔感を意識する |
手水舎の装飾と龍のモチーフの意味
神社で手を洗うところは「手水舎(ちょうずや・てみずや)」と呼ばれます。この場所にはしばしば龍が装飾として用いられています。龍は日本の神話や信仰において水を司る神聖な存在とされており、神社の手水舎では清らかな水をもたらす象徴として重用されています。龍の口から流れる水で手や口を清めることで、参拝者は心身ともに浄化され、神域に相応しい状態となります。
手水舎の装飾は神社ごとに異なり、伝統的な木造建築に加え、石や銅を使った美しい彫刻が施されていることも多いです。龍の他にも鶴や亀、植物などが取り入れられることもあり、それぞれに意味が込められています。神聖な場所で手を清めるという日本文化の美学が、手水舎の細部にまで表現されています。
龍がモチーフに使われる理由
龍は古来より水の守り神として信仰されてきました。手水舎に龍が使われるのは、参拝者がその水で穢れを落とし、清らかな気持ちで神様に向き合うための意味が込められています。龍の口から流れる水は、神聖な生命の源とされ、神社と人をつなぐ重要な役割を果たします。
また、龍は豊穣や厄除けの象徴でもあり、手水舎に設置されることで神社全体のご利益や安心感を強調しています。下記のテーブルで龍がモチーフとなっている手水舎の一部を紹介します。
| 神社名 | 地域 | 龍の特徴 |
| 明治神宮 | 東京 | 青銅製の龍が水を吐いている |
| 伏見稲荷大社 | 京都 | 木彫りの龍の細工が美しい |
| 伊勢神宮 | 三重 | シンプルな石造りの龍 |
| 氷川神社 | 埼玉 | 迫力ある龍の彫刻が印象的 |
地域ごとの特徴的な手水舎デザイン事例
全国の神社では、地域性を反映した手水舎のデザインが見られます。関西地方では木彫りの細工が多く、京都の神社は花や植物の彫刻が特徴的です。関東地方の神社では石や銅を使ったシンプルなデザインが多く見られます。北陸や東北地方では雪に強い屋根付きの手水舎も一般的です。
特に最近は、観光客や若い世代にも人気の「花手水」が話題です。花手水は、手水鉢に季節の花を浮かべて彩るもので、SNSでも多くの写真が投稿されています。地域ごとに異なる花や装飾が施され、神社巡りの楽しみの一つになっています。
- 木彫りや石彫刻による地域独自の装飾
- 季節の花を使った花手水の実施
- 雪国では屋根付き手水舎が多い
- 観光スポットとしても人気が高まっている
現代アートとしての花手水・手水舎
近年、手水舎の新しい取り組みとして「花手水」が全国で広がっています。これは手水舎の水盤に色とりどりの花を浮かべ、訪れる人の目を楽しませる現代アートの一形態です。花手水は伝統と現代美術が融合した新たな神社文化として注目され、京都や東京などの都市部でも多くの神社が取り入れています。
花手水の魅力は、季節ごとに異なる花を使うことで何度訪れても新鮮な体験ができる点です。SNS映えする美しさもあり、写真撮影の人気スポットとなっている神社も少なくありません。伝統的な手水舎の役割を守りつつ、現代的な美意識と調和した新しい参拝体験を生み出しています。
- 季節感を演出する新しい神社文化
- 参拝者の体験価値向上
- 全国各地で多様な花手水が誕生
手水舎の衛生面と現代の利用上の配慮
神社の境内にある手水舎は「てみずしゃ」と読み、参拝前に心身を清めるための場所です。日本文化や伝統に深く根付いたこの施設は、全国の神社や寺院で見られ、地域によっては「手水所」「手水場」「手水屋」と呼ばれることもあります。手水舎の多くには龍の装飾があり、これは水神としての意味合いからきています。最近では「花手水」と呼ばれる、花を浮かべた美しい手水舎も人気で、写真スポットとしても親しまれています。
衛生面の配慮も重視されており、特に多くの人が利用する大きな神社では、定期的な清掃や水の入れ替えが行われています。手水舎の水は流れ続けていることが多く、清潔が保たれています。利用者も柄杓の持ち方や手の洗い方など、正しい作法を身につけることで、衛生的に利用することができます。
口をすすぐ時の正しい方法と吐き出し場所
手水舎での口すすぎは、参拝のマナーとして重要な作法です。まず、柄杓で左手・右手の順に洗った後、もう一度水をすくって左手に取り、その水で口をすすぎます。直接柄杓に口をつけるのは避けてください。
口をすすいだ水の吐き出し場所については、足元にある排水溝や、手水鉢の下に流すのが一般的なマナーです。周囲に人がいる場合は、静かに吐き出し、飛び散らないように注意しましょう。
正しい手順をまとめると以下のようになります。
- 柄杓で左手を洗う
- 柄杓で右手を洗う
- 左手に水を受けて口をすすぐ
- 再度左手を洗う
- 柄杓を立てて柄を清めて戻す
この手順を守ることで、清潔かつ気持ちよく参拝ができます。
新型感染症対策下の手水舎利用の変化
近年の新型感染症拡大により、手水舎の利用方法にも変化が見られます。多くの神社では柄杓の共用を控えたり、流水のみで手を清めるスタイルを導入しています。また、一部の神社では手水舎自体を一時的に閉鎖している場合もあります。
感染予防の観点からは、口をすすぐ動作を省略し、手洗いのみで済ます参拝者も増えています。マスク着用や、使用後の手拭き用ハンカチの持参も推奨されています。来訪前に各神社の公式サイトや案内を確認することで、安心して参拝できます。
手水舎の清掃やメンテナンス状況
手水舎は多くの参拝者が利用するため、神社側は衛生管理に特に注意を払っています。水は定期的に入れ替えられ、柄杓も毎日清掃されています。花手水を実施している神社では、花の交換や水質管理も徹底されています。
利用者としても、次の点に注意しましょう。
- 柄杓は他の部分に触れずに使う
- 使い終わったら元の場所に戻す
- ゴミや私物を手水舎に残さない
下記のテーブルで、手水舎の衛生面と利用マナーを整理します。
| 注意点 | 推奨される行動 |
| 柄杓の使い方 | 他人と共用しない |
| 口すすぎの方法 | 柄杓に口をつけない |
| 水の吐き出し場所 | 排水溝を利用 |
| 手拭き用タオル | 各自で持参し使用 |
| 花手水の鑑賞 | 水や花に直接触れない |
衛生面に気を配りながら、伝統を尊重して参拝することで、快適な神社体験を楽しめます。
大稲荷神社は、古くから地域に親しまれている神社で、心安らぐひとときを提供しています。歴史的な背景を持ち、神聖な空間の中で心を込めたお祓いや祈願を行っております。境内では、静寂な雰囲気の中で自然と調和したひとときを楽しんでいただけます。地元の方々はもちろん、訪れる方々にとっても安らぎと力を与える場所となっております。どうぞ一度お参りいただき、神聖な空間を体験してください。

| 大稲荷神社 | |
|---|---|
| 住所 | 〒250-0045神奈川県小田原市城山1-22-1 |
| 電話 | 090-3478-4699 |
アクセス
名称・・・大稲荷神社
所在地・・・〒250-0045 神奈川県小田原市城山1-22-1
電話番号・・・090-3478-4699